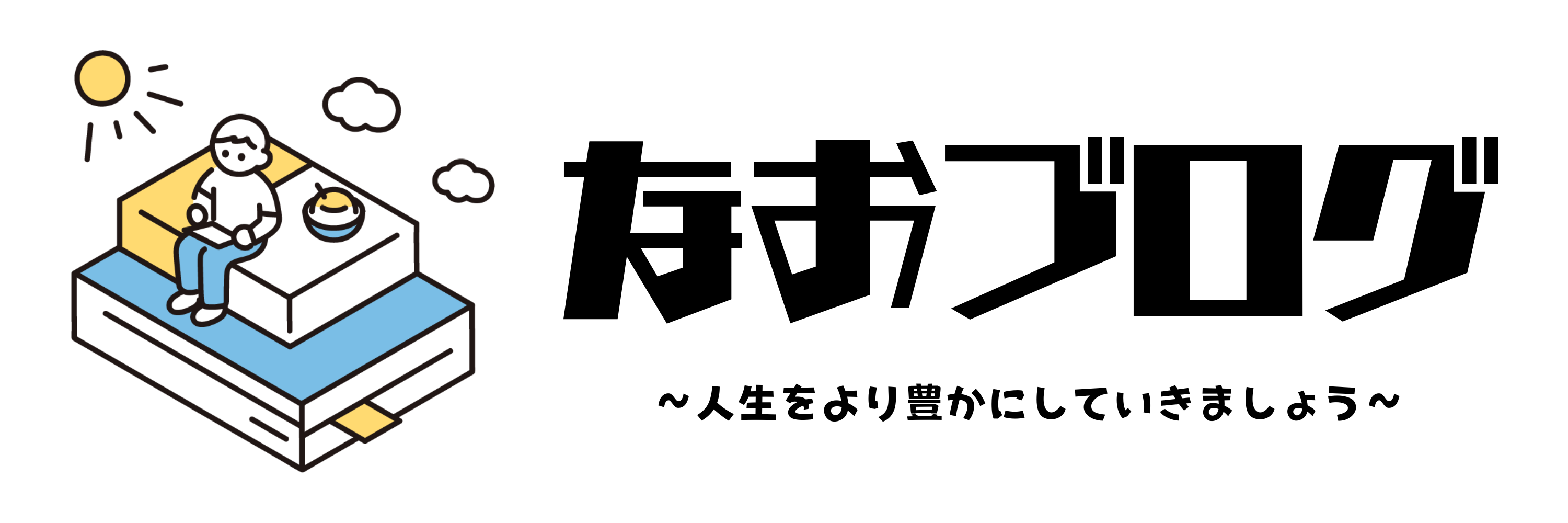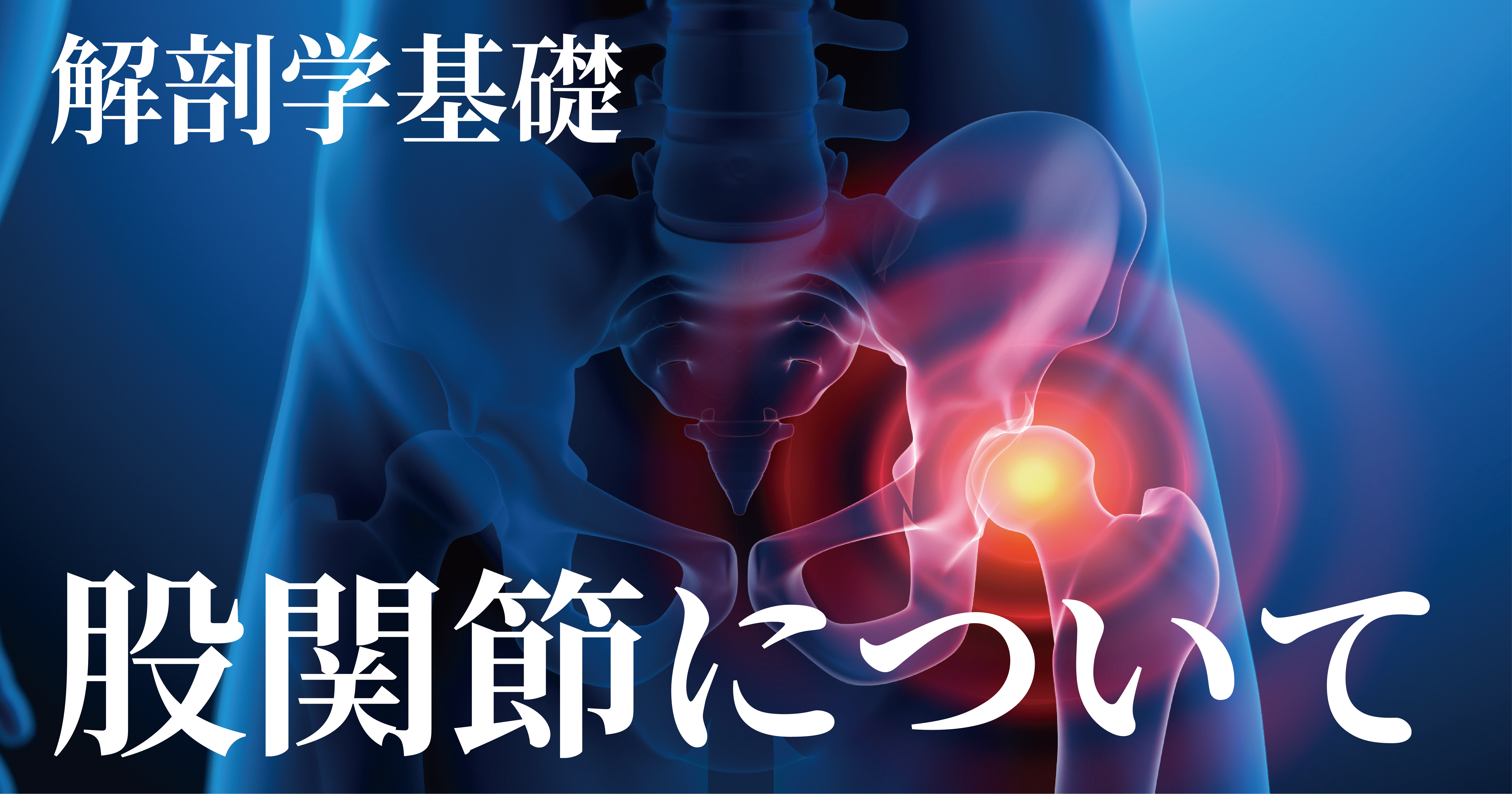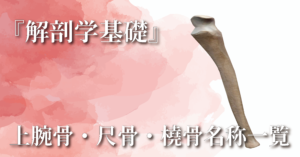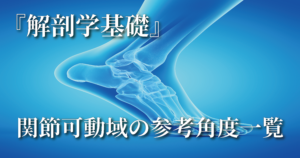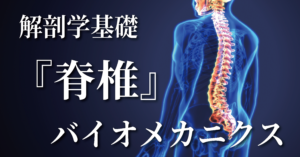概要
股関節は、寛骨臼と大腿骨頭からなる臼状関節である。(寛骨臼大腿関節ともいう)
また多軸関節でもあり、肩関節に次いで最も動きのある関節と言えます。
股関節の役割として荷重の受け止めなどがある。(荷重関節)
※寛骨臼は深いため大腿骨頭を覆う面積が大きい=安定性が高い(肩関節と比べて、亜脱臼などはしにくい)
安定性が高い=運動性が低くなる(肩関節と比較すると明確である)
股関節の動作
屈曲
腿を上げる動き
主動筋
- 大腰筋
- 腸骨筋
- 大腿直筋
- 縫工筋
- 大腿筋膜張筋
- 恥骨金
- 長内転筋
協力筋
- 短内転筋
- 薄筋
伸展
脚を後ろへ蹴る動き
主動筋
- 大臀筋
- 大腿二頭筋(長頭)
- 半腱様筋
- 半膜様筋
- 大内転筋(後部繊維)
協力筋
- 中臀筋
- 大内転筋(前部繊維)
内転
脚を内側へ閉じる動き
主動筋
- 長内転筋
- 短内転筋
- 大内転筋
協力筋
- 恥骨筋
- 薄筋
外転
脚を外側へ開く動き
主動筋・協力筋
- 中臀筋
- 小臀筋
- 大腿筋膜張筋
協力筋
- 縫工筋
- 大臀筋
- 梨状筋
内旋
脚を内側へ捻る動き
主動筋・協力筋
- 中臀筋(前部繊維)
- 小臀筋(前部繊維)
- 大腿筋膜張筋
外旋
膝を外側へ捻る動き
主動筋・協力筋
- 大臀筋
- 梨状筋
- 大腿方形筋
- 外・内閉鎖筋
- 上・下双子筋
協力筋
- 中臀筋(後部繊維)
- 小臀筋(後部繊維)
- 縫工筋
股関節の安定化機構
静的安定化機構
骨形態:関節窩の深さには個体差があり、臼蓋形成不全が存在することもある。
寛骨臼形成不全(臼蓋形成不全)とは、寛骨臼の形成が不十分で、被覆が浅い(股関節の屋根が浅い)疾患です。 アジア人、特に日本人に多く、成人男性0〜2%、女性2〜7%が寛骨臼形成不全と言われており、女性に多いことがこの疾患の特徴です。 荷重部が狭く、部分的に負荷がかかり、その状態が続くとその部分の軟骨がすり減っていきます。
東京慈恵医科大学附属第三病院整形外科HPより引用
関節唇:関節窩の深さを補う繊維軟骨組織。前上方を損傷することが多い
関節包・靭帯:3つの関節包靭帯が安定性に寄与する
- 腸骨大腿靭帯:3つの中で最も強力
- 恥骨大腿靭帯:恥骨から股関節前面を覆う
- 坐骨大腿靭帯:後面から上方を回り込む
動的安定化機構
■深層外旋六筋:関節窩に大腿骨頭を引き付ける肢位をとる
※大腿方形筋、梨状筋、内・外閉鎖筋、上・下双子筋の6筋からなる。
■小臀筋:股関節の上面を通過し、大転子の前方に向かう外転筋
■腸腰筋:股関節屈曲時に大腿骨頭を後方に押し付ける作用があると考えられる。
※腸骨筋、小腰筋、大腰筋の総称。
股関節の運動
股関節の運動は、股関節独自の運動と骨盤の運動が複合して生じている。
■骨盤大腿リズム
①大腿骨が骨盤に対して屈曲すると、骨盤は後傾位になる
②大腿骨は頸部に前捻角と後捻角が存在するため
- 股関節屈曲運動では大腿骨頭の内旋が生じる
- 股関節伸展運動では大腿骨頭の外旋が生じる
股関節の動作不全、またトレーニングへの弊害
股関節の可動制限が起こる原因
股関節の可動制限が起こる原因として
- 股関節周辺の筋肉の張力関係の乱れ(強弱の差が大きい)
- 股関節周辺の軟部組織の硬さ
- 関節砲の硬さ
などが挙げられます。
その原因に対して、適切なアプローチを行うことが重要になります。
例)筋肉の硬さ=ストレッチ/マッサージなど
※実際のケースでは、根本的な要因は他の場所である可能性が高いので広い視点での動作分析を心がけましょう。
股関節の可動制限によるトレーニングの影響
- 可動制限により、筋肉の最大短縮、伸展させることができずにトレーニング強度が下がる
- 可動域を超えて運動動作を行なった場合、代償運動が起こり他の部分へのストレスが発生する
参考文献・資料
■身体運動の機能解剖学 改訂版 著者:Clem W.Thompson, R.T.Floyd
■運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略 編著:工藤 慎太郎
■Anfida オンラインサロン 運営者:宮城島 大樹
■アナトミーアトラス